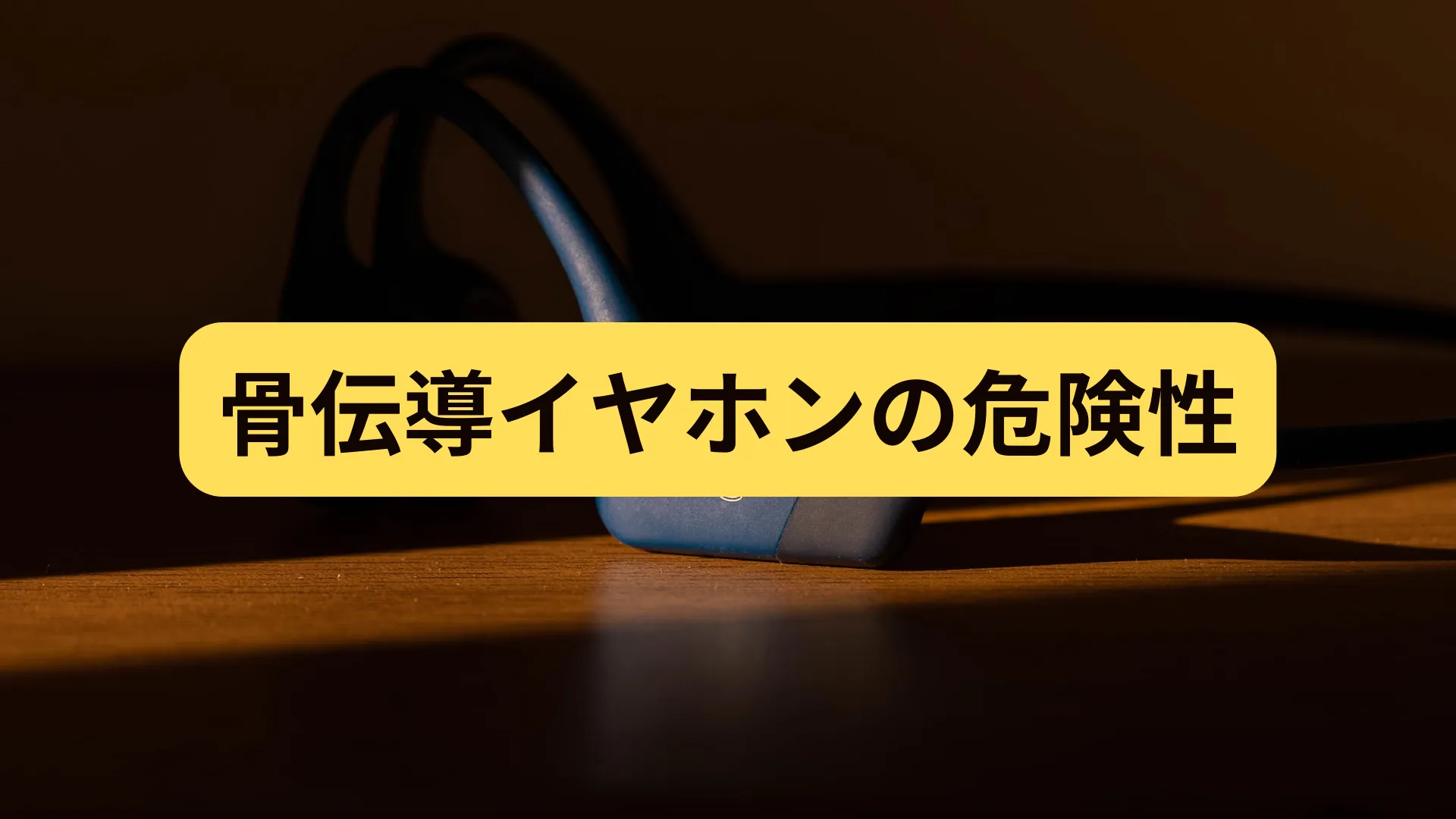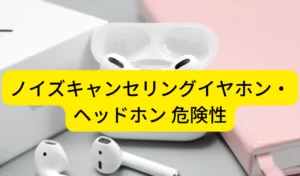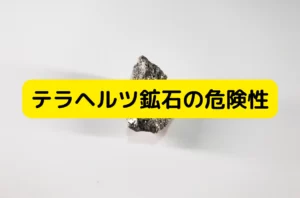骨伝導イヤホンの原理からメリット・リスクについて解説
最近、「骨伝導イヤホン」という新しいタイプのイヤホンが流行していますよね?
中には、すでに骨伝導イヤホンを使っている方もいらっしゃるのではないしょうか。
骨伝導技術を用いたイヤホン製品は、空気の振動を介さずに、直接、頭部の骨を振動させることで音を聴覚に伝えています。
しかし、骨に響かせて音を聴くとなると、「脳や耳に危険性があるのでは?」と不安に思う方もいるかもしれません。実際、骨伝導イヤホンは危険なのでしょうか。
今回は、骨伝導イヤホンの原理からメリット・危険性にいたるまで幅広く解説していきます。
この記事を執筆した専門家

医師。プライマリ・ケア認定医、外科専門医、病院総合医療認定医。
現在、内科・外科・皮膚科医として勤務する医学分野の専門家。
骨伝導イヤホンの原理
本来、音は耳から聞いて脳に信号として伝えているのはご存じですよね。
実際、人は空気の振動を耳から鼓膜へと受けとり、それを声や音楽などの音として感じています。この振動は耳の穴を通り、鼓膜を振動させることで耳の奥にある蝸牛(かぎゅう)という部分に届きます。
蝸牛はその名の通りカタツムリのような形をしていて、音の情報を脳に伝える役割を担っています。これが本来の音の伝わり方です。
しかし、骨伝導はこうした経路のうち一部分を省略します。骨伝導は耳や鼓膜を経由せずに、耳周辺の骨を振動させて、その振動が蝸牛へと届く仕組みになっているのです。そのため、私たちは鼓膜ではなく、蝸牛で音を聞いています。
つまり、鼓膜を使っても骨伝導であっても、蝸牛に適切な振動が届けば、音は聞こえるのです。一例として、煎餅のような固い食べ物を食べる時、私たちが聞こえるそしゃく音は顔の骨を通して内耳に振動として伝わっているものです。
これを応用したものが、「骨伝導イヤホン」。骨伝導イヤホンでは、耳周辺の骨を振動させることで、蝸牛へ音を届ける仕組みになっています。
ただし、骨伝導で音を聞くときの仕組みについて、まだ完全には解明されていません。振動がどのように蝸牛へ伝わり、音が聞こえているのか、詳しいメカニズムについては曖昧な部分があります。
骨伝導の危険性は?いいえ、むしろ安全です。
コロナ禍の中、オンライン会議などでイヤホンが必需品になった方も多いと思います。しかし、イヤホンで大きい音を長時間にわたって聞くと、耳に負荷がかかり続けて音が聞こえにくくなる可能性があると言われています。
大きな音にさらされることで起こる難聴を騒音性難聴あるいは音響性難聴といいます。騒音性難聴は主に、職場で工場の機械音や工事音などの騒音にさらされることで起こります。
一方、音響性難聴は、爆発音あるいはコンサート・ライブ会場などの大音響などにさらされるほか、ヘッドホンやイヤホンで大きな音を聞き続けることによって起こります。後者は「ヘッドホン難聴」あるいは「イヤホン難聴」と呼ばれ、近年、特に問題視されています。

WHO(世界保健機関)では、11億人もの世界の若者たち(12〜35歳)が、携帯型音楽プレーヤーやスマートフォンなどによる音響性難聴のリスクにさらされているとして警鐘を鳴らしています。
耳から入った音は、蝸牛にある有毛細胞という細胞で振動から電気信号に変換され、脳に伝わることで聞こえるようになります。自動車の騒音程度である85dB(デシベル)以上の音を聞く場合、音の大きさと聞いている時間に比例して、蝸牛の有毛細胞が傷つき、壊れてしまいます。有毛細胞が壊れると、音を感じ取りにくくなり、難聴を引き起こします。
ヘッドホン難聴(イヤホン難聴)は、じわじわと進行し、少しずつ両方の耳の聞こえが悪くなっていくため、初期には難聴を自覚しにくいことが特徴です。重症化すると聴力の回復が難しいため、そのような耳の違和感に気づいたら早めに受診することが大切です。
この予防策として期待されているのが、過度に音量を上げなくても音楽が聴き取りやすい「骨伝導イヤホン」です。鼓膜を酷使することがないため、聴力の低下防止に役立つのではないかと期待されています。
また、電磁波についてもほかの電気製品と同じように発生していますが、ごく微弱なものです。自然界に存在する電磁波と同レベルの強さで、特別、脳への影響も懸念されていません。
骨伝導イヤホンは難聴者でも使える?
では、鼓膜を介さずに音を届ける骨伝導イヤホンは、難聴の方でも使えるのでしょうか?
研究結果では「難聴の方にも骨伝導イヤホンは有用」とされています。
特に、鼓膜や耳小骨など外耳から中耳にかけてのみに障害があると考えられる、軽度から中度の聴覚障害者では、骨伝導によって聞こえる可能性があるのです。
感音性難聴の場合は、内耳もしくは中枢に障害がある可能性が高いため、骨伝導音を用いたとしても「信号」としては届いているはずですが、その後の音を「音として知覚する」ところで問題が生じているため聞こえないない場合が多いです。
骨伝導はさまざまな音響機器に応用することが可能ですが、耳鼻咽喉科の分野では補聴器への応用が考えられます。

現在、販売されている補聴器のほとんどが気導補聴器(空気の振動)です。骨伝導の補聴器は、効果を維持するために音を伝える振動子をヘッドバンドで骨に強く固定しなければなりません。
そのため、痛みや凹みなどで、長時間の装用が難しいのが難点です。また、技術的な問題から重度の難聴には対応することができないため、骨伝導の補聴器の多くは、重度難聴者には使われません。
最近では、耳の軟骨部に振動を与えてきこえを補う、新しいタイプの補聴器も登場しています。
骨伝導イヤホンのメリット・デメリット
このように、難聴の方にも効果がある骨伝導イヤホン。そのメリット、デメリットについて詳しくみていきましょう。
骨伝導イヤホンのメリット
①周囲の音を聞きながら音声を聞くことができる
一般的にヘッドホンは外の音を遮断するものですが、サイクリングやランニングなど運動中に外の音を遮断してしまうと、危険をともなう場合もあります。そんなときに耳を塞がない骨伝導ヘッドホンを使えば、外の情報を遮断せずに、音楽などを楽しむことができます。
②鼓膜を介さないので、耳が疲れにくい
ヘッドホンやイヤホンで長時間音楽を聴いていると、鼓膜が疲れたり、耳が塞がれ続ける圧迫感を感じることもあります。その点骨伝導イヤホン・ヘッドホンは、そもそも耳に入れないので、耳を疲れさせることなく長時間音楽を聴くことができます。
③耳の穴が小さくても使える
耳の穴が小さい人が普通のイヤホンを使っていると、耳の穴に入れづらかったり、抜けやすくなったりする場合があります。骨伝導イヤホンの場合、耳の穴の大きさは入れやすさ、抜けやすさに関係ありません。

骨伝導イヤホンのデメリット
①音質があまりよくない。音が小さく感じる。
普通のヘッドホンやイヤホンと比べると、音質があまり良くなかったり、ボリュームを上げないとうまく聞こえない点はデメリットです。イヤホンによっては専用のアプリを使って音質を高められるモデルもあります。
②音が外に漏れやすい
音量を上げて聞く必要がある骨伝導イヤホンは、普通のイヤホンに比べて、音漏れが気になります。電車やバスなどでの使用には向いていません。
このように、優れた骨伝導イヤホンでもメリット・デメリットがあります。イヤホンを使う場面に合わせて、適切なイヤホンを使っていきたいですね。
骨伝導イヤホンのまとめ
今回は骨伝導イヤホンの原理から危険性、メリット・デメリットに至るまで幅広く解説していきました。まとめると以下のようになります。
- 骨伝導イヤホンは鼓膜を介さずに蝸牛に電気信号を伝えることで、音の情報を脳に伝える仕組みになっている。
- 近年、イヤホンの使い過ぎによる「ヘッドホン難聴」が深刻化しており、骨伝導イヤホンはそれを防ぐ効果が期待されている。
- 難聴の方も骨伝導イヤホンは使いやすく、特に鼓膜での障害を受けている方には骨伝導イヤホンが有用である可能性がある。
- ただし、音が外に漏れやすかったり、音質がよくなかったりなどのデメリットもあるため、場面に合わせて使い分ける必要がある。
骨伝導イヤホンも正しく使うと非常に便利なツールです。ただし、使い過ぎてスマホ依存にならないようご注意ください。